
健康保険を扱っている病院、診療所へ被保険者証等を提示すれば給付が受けられます。
| 年齢 | 義務教育就学前※ | 義務教育就学時から69歳まで | 70歳以上 (一般) | 70歳以上 (現役並み所得者) |
| 一部負担割合 | 医療費の2割 | 医療費の3割 | 医療費の2割 | 医療費の3割 |
※6歳に達する日以降の最初の3月31日以前
やむを得ない理由で、非保険医にかかったとき、被保険者証等を提示できなかったときなどは、いったん費用の全額を支払い、あとから申請することにより支給されます。
※自己負担額が21,000円を超えた場合、高額療養費の合算対象となります 。
(2)緊急その他やむを得ない理由で被保険者証等を提示できなかったときの医療費
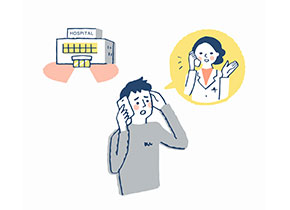
必要書類
添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・療養費支給申請書
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
(3)医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具代

必要書類
添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・療養費支給申請書
・領収書(写)
・靴型装具の場合のみ装具の写真添付が必要
・医師の証明書※
(4)はり、灸、マッサージなどの施術料で医師が必要と認めたとき

必要書類
添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・療養費支給申請書
・領収書(写)
・医師の同意書
(5)骨折、ねんざで柔道整復師の施術を受けたとき

必要書類
添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・療養費支給申請書
・施術料金明細書
(6)海外で治療をうけたとき

必要書類
添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・療養費支給申請書
・診療内容明細書
・領収明細書
・パスポート等の写し(渡航期間を確認できるもの)
・療養内容の照会に関する同意書
1か月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、申請をすると高額療養費として支給されます。
入院・外来ともに「限度額適用認定証」などを窓口に提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります(現物給付)。
「限度額適用認定証」などを提示しない場合は、いったん一部負担割合に応じた窓口負担分を支払い、あとから申請することにより支給されます(償還払い)。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※「限度額適用認定証」などの交付については、所属支部へご連絡ください。
※保険料を滞納している場合、「限度額適用認定証」などの交付はできません。
※70歳以上の一般所得の方は、「限度額適用認定証」などは不要です。
「限度額適用認定証」などの交付
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・国民健康保険 限度額適用/限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(様式13)
・「高額療養費自己負担限度額」判定申請書
・実態調査報告書(自損事故等の場合)
判定により、低所得の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、70歳未満の一般所得・上位所得の方と70歳以上の現役並み所得の方には「限度額認定証」が交付されます。
70歳以上の一般所得の方は「被保険者証兼高齢受給者証」により所得区分が確認できるため、交付されません。
70歳以上の「現役並み所得Ⅲ」に該当する方も、交付されません。
償還払い(限度額適用認定証を提示しなかった場合)の申請
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・高額療養費支給申請書(様式6-2)
・領収書
・「高額療養費自己負担限度額」判定申請書
・令和6年7月診療分の申請から、手続きの簡素化が可能となりました。
詳しくは「高額療養費支給該当の皆様へ」をご確認ください。
自己負担限度額
70歳未満・世帯全体
| 所得要件 | 限度額 |
| 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
| 旧ただし書所得 600万円~901万以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 |
| 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 (44,400円)※1 |
| 住民税非課税 | 35,400円 (24,600円)※1 |
※1 ( )内の額は、多数該当(12か月間で4回目以降)の場合。
※2 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した金額です。
※3 同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合に、自己負担額を合算し、一定額を超えた金額が申請により支給されます(世帯合算)。
70歳以上
| 所得区分 | 所得要件 | 限度額 | |
| 外来 (個人ごとに計算) |
入院又は世帯単位 | ||
| 現役並所得Ⅲ | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (140,100円)※1 |
|
| 現役並所得Ⅱ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (93,000円)※1 |
|
| 現役並所得Ⅰ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)※1 |
|
| 一般 | 課税所得 145万円未満 ※2 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (44,000円)※1 |
| 低所得Ⅱ ※3 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ ※4 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 | |
※1 ( )内の額は、多数該当(12か月間で4回目以降)の場合。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。それに加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 同一世帯内の世帯主及び国保被保険者(70歳未満含む全員)が住民税非課税の方。
※4 同一世帯内の世帯主及び国保被保険者(70歳未満含む全員)が住民税非課税であり、その世帯の所得が一定の基準に満たない方。
世帯に介護保険の受給者が存在する場合、毎年8月~7月までの支給対象期間内で医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、高額介護合算算定基準額(限度額)を超えた場合に支給されます(差額が500円を上回らなければ、支給対象外)。
支給額は、各保険の自己負担額により按分され、各保険者より支給されます(建築国保からは、医療保険の自己負担額によって分配される金額が支給されることになります)。
高額介護合算算定基準額
70歳未満
| 所得要件 | 限度額 |
| 旧ただし書所得 901万円超 |
2,120,000円 |
| 旧ただし書所得 600万円~901万以下 |
1,410,000円 |
| 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
670,000円 |
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
600,000円 |
| 住民税非課税 | 340,000円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した金額です。
70歳以上
| 所得区分 | 所得要件 | 限度額 |
| 現役並所得Ⅲ | 課税所得 690万円以上 |
2,120,000円 |
| 現役並所得Ⅱ | 課税所得 380万円以上 |
1,410,000円 |
| 現役並所得Ⅰ | 課税所得 145万円以上 |
670,000円 |
| 一般 | 課税所得 145万円未満 ※1 |
560,000円 |
| 低所得Ⅱ※2 | 住民税非課税 | 310,000円 |
| 低所得Ⅰ※3 | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
190,000円 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。それに加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 同一世帯内の世帯主及び国保被保険者(70歳未満含む全員)が住民税非課税の方。
※3 同一世帯内の世帯主及び国保被保険者(70歳未満含む全員)が住民税非課税であり、その世帯の所得が一定の基準に満たない方。
入院中の食費のうち、本人が負担する標準負担額を控除した額が支給されます(現物給付)。
入院時の食費にかかる標準負担額
| 区分 | 標準負担額 (1食分) |
|
| 一般 | 下記以外 | 510円 |
| 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 | 300円 |
|
| 非課税世帯及び 低所得Ⅱ |
90日まで | 240円 |
| 90日を超える (過去12か月の入院日数) |
190円 | |
| 低所得Ⅰ | 110円 | |
※令和7年4月から標準負担額が改正されました。
療養病床に入院する65歳以上の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水)に要した費用のうち、本人が負担する標準負担額を控除した額が支給されます(現物給付)。
| 区分 | 標準負担額 | ||
| 食費(1食分) | 居住費 (1日分) |
||
| 一般 (下記以外) |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 510円 ※難病患者300円 |
370円 ※難病患者0円 |
| 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 470円 ※難病患者300円 |
||
| 非課税世帯及び低所得Ⅱ | 240円 | ||
| 低所得Ⅰ | 140円 | ||
| 境界層該当者 | 110円 | 0円 | |
※入院医療の必要性の高い患者の負担については、入院時食事療養費の標準負担額と同額。
※令和7年4月から標準負担額(食費)が改正されました。
厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養を受けた場合に支給されます。
居宅において継続して療養を受ける状態にある方が、主治医の指示に基づき訪問を受けた場合に支給されます。
疾病又は負傷により移動が困難な方が、医師の指示により、緊急その他やむを得ず移送されたときに支給されます。
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・国民健康保険移送承認申請書(様式10)
・国民健康保険移送料請求書(様式11)
・領収書
被保険者(組合員、家族)が出産したときに支給されます。
| 支給額 | 500,000円 (488,000円) |
| 支払方法 | 直接支払制度による支払い 及び償還払い、受取代理制度による支払い |
※支給額( )内の金額は産科医療補償制度対象外の分娩の場合。
直接支払制度
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる制度です。
直接支払制度の上限…500,000円
出産費用が直接支払制度の上限に満たない場合、差額を支給いたします。
なお、医療機関等が直接支払制度に対応していない場合、又は、出産育児一時金が建築国保から医療機関等に直接支払われることを望まれない場合は、出産後に当組合から受け取る従来の申請方法をご利用ください。
(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
直接支払制度の申請
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・出産育児一時金支給申請書(様式7)
償還払いの申請
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
受取代理制度の申請
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・出産育児一時金等請求書(受取代理用)
・母子手帳の写し
産前産後期間の国民健康保険料軽減措置の届出
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
(共通)
・産前産後期間の保険料軽減措置届出書
(出産後の届出の場合)
・母子健康手帳の表紙の写し と 母子健康手帳の出生届済証明ページの写し または「出生証明書」や「世帯全員の住民票」等、出生日が確認できるもの
(出産前の届出の場合)母子健康手帳の以下3ページ
・母子健康手帳の表紙の写し
・母子健康手帳の保護者欄記載ページの写し
・母子健康手帳の分娩予定日記載ページの写し
産前産後期間の国民健康保険料軽減措置については「保険料」ページをご確認ください。
被保険者(組合員、家族)が死亡したときに支給されます。
■組合員 ...100,000円
■家族 ...50,000円
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・葬祭費支給申請書(様式8)
・死亡診断書又は埋葬許可書等事実を証明できるもの
・葬儀を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、葬儀会社の領収書等)
組合員が病気やケガ(労災、第三者行為は除く)で入院したときに支給されます。
■1級 ...1日6,000円×60日以内
■2.3.4級...1日5,000円×60日以内
※ただし、自損事故(ケガ)によるものは、4日間の免責期間を設け、5日目から10日目までの6日間を限度に支給します。
なお、法令違反によるものは、支給されません。
また、同一疾病については、5年毎に適用になります。
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・傷病手当金支給申請書(様式9-1)
・実態調査報告書(自損事故(ケガ)の場合)
組合員(組合員として加入後1年以上経過)が出産したときに支給されます。
■1児につき300,000円
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・出産手当金支給申請書(様式9-2)
・母子手帳の写し
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合、被保険者証等を使用して治療を受けることはできますが、その治療費は加害者が負担すべきものです。
建築国保は、治療費を一時的に立て替え、後から加害者に請求します。
必ず、建築国保へ届出を行い、承認を受けてから保険診療を受けてください。
※示談のときは建築国保に必ず相談してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立してしまうと、建築国保も示談の内容に従わなければいけません。
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・交通事故実態調査報告書(pdf)
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書(pdf)
・第三者行為による傷病届(pdf)
・同意書(pdf)
・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手不能な場合)
交通事故以外の第三者行為(けんかや動物などによるケガ)の被害者になった場合の申請
必要書類 添付書類は「写し」と記載のあるもの以外は原則「原本」を提出
・自損事故・第三者行為実態調査報告書(pdf)
第三者行為以外のケガ(階段から落ちた、スポーツで負傷したなど)で被保険者証等を使用し、医療機関を受診した場合は、建築国保へ届出が必要です。
また、仕事中のケガや病気(熱中症など)については、労災保険で治療を受けるのが原則です。止むを得ず被保険者証等を使用し、医療機関を受診した場合は、建築国保へ届出が必要となります。
(c) Niigata Prefecture kenchiku-kokuho All Right Reserved.